「やる気はあるのに、どうして続かないんだろう」「自分ってやっぱり意志が弱いのかも…」
何かを続けようとして挫折したとき、こんなふうに落ち込んでしまうことはありませんか? でも実は、それは「自分がダメだから」ではなく、“仕組み”が整っていないからかもしれません。
この記事では、心理的・物理的な障害を減らし、気合に頼らず自然と続く暮らしをつくるための私なりの考え方と具体例をご紹介します。
システムで迷いを減らして、やりたいことに集中できる仕組み提案する 「仕組み化で、頑張らなくても続く暮らしシリーズ」その2。
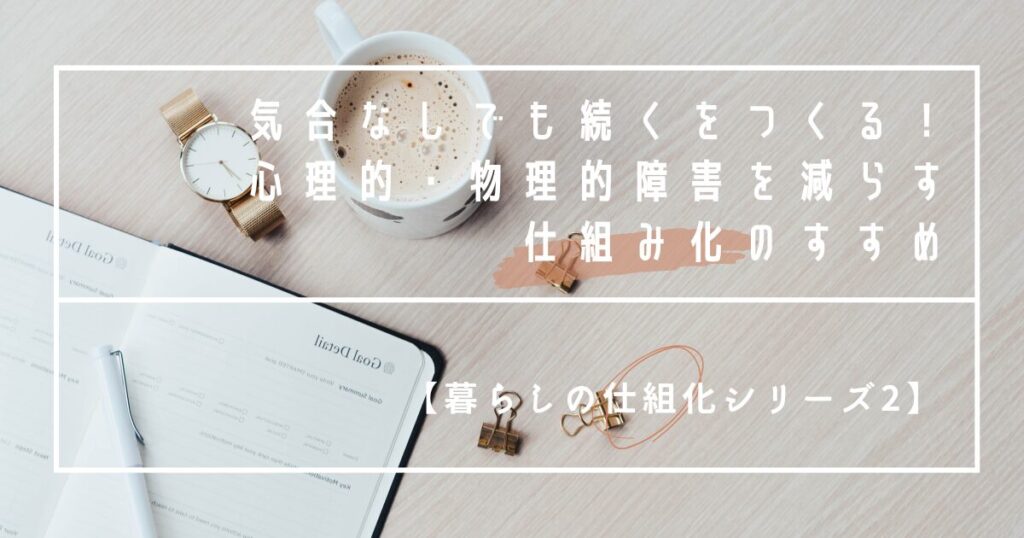
続かないのは、気合の問題じゃない
私たちの脳は、意外とすぐに疲れてしまうもの。 判断や決断の回数が増えるだけで、脳のエネルギーはどんどん消耗されます。
たとえば、朝から 「今日何を着よう」「何を食べよう」「何から片付けよう」と悩んでいると、 午前中だけでエネルギー切れ…なんてことも。
つまり、「続けられない」「やる気が出ない」の多くは、脳疲労や環境的な障害のせいかもしれません。
「つまずきポイント」を見える化しよう
まず大事なのは、「どこで続かなくなるか?」を見える化することです。
たとえば…
・献立を考えるのが面倒で外食が増える
・家計簿をつけようとしても続かない
・服が多くて選ぶのに疲れて毎朝バタバタ
つまづきポイントは主に②種類あります。
これらにはすべて、心理的な障害(面倒・不安・やる気の出なさ)と、 物理的な障害(モノが多い・場所が遠い・時間ががかかる)が関係しています。
習慣化するための工夫
実際にどれもやってみて効果があったものをご紹介します。
▷ 心理的な障害を減らすには
▷ 物理的な障害を減らすには
脳が気づかずに、拒否反応を示せないくらい小さく素早く始めることがポイントです。
PC作業ならパソコンを視界に入れる、触る、開く…それほど小さく慣らしていきました。
続くかどうかは「準備」で決まる
続けようとする前に「やるか・やらないかの判断」をしている時点で、もう脳は消耗しています。
だから、「やることを考える」よりも、「やれる状態を用意しておく」ことが大事です。
たとえば…
・献立はあらかじめ“困ったとき用メニュー”を決めておく
・家計簿は項目をしぼって「とりあえず書くだけ」にする
・洋服は「気に入った同じ系統」を揃えておく
“迷わないようにする”ことで、習慣は気合いではなく仕組みで回るようになります。
▼“すぐ決まる暮らし”で脳の疲れが激減!迷わない仕組みづくりのすすめ【仕組化シリーズ1】
習慣は「自分を助ける仕組み」に変えられる

わたし自身、献立や家計簿、片づけ、服選びなど、「なんとなく続かないこと」に悩んできました。 でも、それぞれに「迷わない」「悩まない」工夫を少しずつ加えていくことで、 気づけば続いている状態になっています。
仕組みづくり=自分への優しさ。 疲れやすい日でも、体調が悪くても、「なにがあってもできる」形にしておくことが、本当の安心につながります。
もちろん、やらないという選択肢もお忘れなく!
続かない自分を責めない仕組み=休憩込みの無理のない設計にしておけば、一度休んでもすぐ戻ってこられます。
【まとめ】気合いに頼らない“続ける力”は、暮らしの土台になる
何かを「始める」よりも、実は「続ける」ほうがずっと難しい。
だからこそ、できない自分を責めるより、どうしたらラクになるか?を考え、気合いに頼らず“勝手に回る”仕組みを育てていくことが、 毎日をもっとラクに、軽やかに変えてくれます。
そして、浮いた時間・お金・エネルギーを「本当に好きなこと」に使えるようになる。
そんな日常づくりのお手伝いができれば幸いです。
次に読むおすすめ記事
👉 【仕組化シリーズ1】 すぐ決まる暮らしで脳の疲れが激減!迷わない仕組みづくりのすすめ
👉 家計簿のつけ方・続け方|お財布とメンタルにやさしい記録術
👉 “日記未満”のこつこつ記録で、自分軸を育てる




