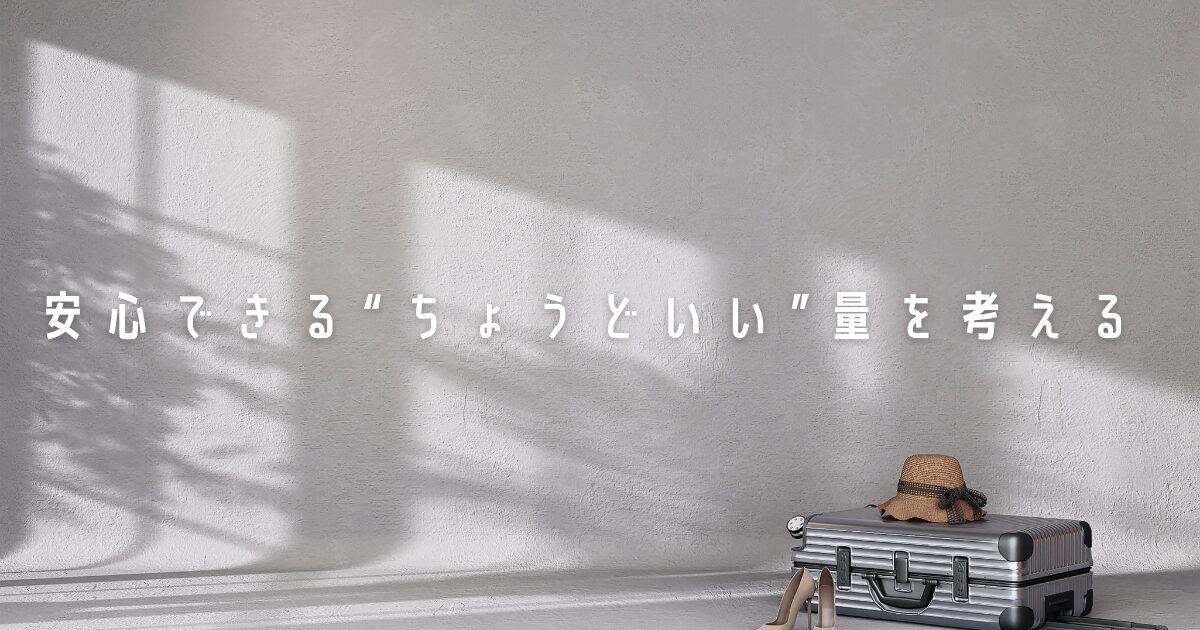あればあるだけ安心なはずの物の管理に疲れてしまって。
ふとした時に、じゃあ「何がどれだけあれば買い物に行かなくて済むのか?」を計算してみたら
気が楽になったのでご紹介してみます。
あなたの安心と安全を確保できる量はどのくらいですか?
一度把握してみることをおすすめします!

持ち物を把握しないデメリット
無計画なまとめ買い、コスパ重視の大容量が生むデメリットを感じたことはありませんか?
在庫管理のメリット
セールに翻弄されないから心が穏やか・節約になる
「安いから」、「せっかく来たから」という理由でなんとなく買うことがなくなりました。
得したい気持ちがしんどさの原因だったのかもしれません。
私はこれだけでかなり気持ちが楽になりました。
底値で買えたらラッキーですが、
セールのたびにソワソワしなくなるので、
得したい気持ちが減ると心にも余裕が生まれます。
「足りないかも」の不安から解放される
淡々と必要量が足りなくなったから買うのみ。
買い物ではスマホにリストを作成しておけば、買い忘れやダブりも防げます。
一覧にするのが大変なほど物を持ち過ぎだと気づくはず。
使用期限内に使い切れる
食品や衣類はもちろん、紙やプラスチックもどんどん劣化していきます。
せっかく安くで手に入れたとしても必要な時に使えない状態では捨てたも同然。
必要なものを使い切るのが、資産と資源にとって一番の節約です。
実は、予期せず余った引越しのご挨拶用の高級ティッシュをもったいなくて使えずにずっと置いていたのですが、
数年で箱もヘニャヘニャになっていて、ティッシュにも期限があるんだなぁと思い知りました。
買い物頻度が決められて時間と体力の温存になる
どのくらいで無くなるのかを把握すれば、なくなるタイミングに余裕をもって購入できます。
収納面積の縮小で足元や室内の安全性が高くなる
置き場所をあらかじめ確保できるので、ストック品をすぐにしまうことができます。
必要量の計算方法
現状を把握する
一度ズラーッと家の在庫を書き出してみてください。結構多くてびっくり。
くじけそうになっても途中で中断できるように、台所・洗面所・風呂場・トイレなど使う場所ごとに分けてみるといいですよ。
消費期間を把握する
商品名の横に開封した日付け、使い終わった日付けをメモしておきます。
必要量を計算する
例365日で割ると1年に必要な量がわかるはず。
切らしたくない期間÷1セットの消費期間=必要量
必要量を維持する
あとは安心できる量を確保しておくだけです。
安心できる量=買い物頻度や入手しやすさ、手間と相談して。
ストック置場の余裕・1パッケージの消費速度も考慮して、残りがどのくらいになったら買うか決めておくといいですね。
楽天お買い物マラソンでまとめ買いしたい人は次のセールまでに消費する分
近所のスーパーでいつでも買えるからストック不要のつどがい派
災害や天候が不安な土地に住んでいて1年分確保したいなど
安心材料はひとそれぞれ。
我が家は
使用中+新品1個を基本ルールにしています。
ただしトイレットペーパーは災害時に無くなりやすく、
かさばるため悪天候で買いに行くのは大変なのでふるさと納税でまとめて注文しています。
防災関連の食品や備品もライフライン復旧までの目安を参考にすれば、
自宅避難の際に安全を脅かしてまで出歩く必要もなくなります。
あなたの安心と安全を確保できる量はどのくらいでしたか?
もし買いたい衝動に駆られたら
リストを再確認する
リストを見てもう十分ある、とわかると落ち着くかもしれません。
なんなら私は増やすどころかリストを減らしたくて、兼用できそうなものにしてみるとか新しい楽しみも生まれました。
もし買うなら気をつけるポイント
全てを計画通りに買う必要はありません。気分転換に買いかえるのもいいですよね。
でもそれを繰り返して今の在庫の山があることをお忘れなく!
まとめ

持ち物の在庫と必要量の把握は、不安からの散財を抑える効果あり。
必要なのは物じゃなくて安心とか、わくわくだったんだなと気づけました。
あなたの安心と安全を確保できる量はどのくらいでしたか?
日用品、非常食、洋服、食品…とジャンルごとに面倒だけど一度きちんと把握してみることをおすすめします!
減ったり増えたりしながら、あなたにとって丁度いい量が見つかりますように。
今回の記事が不安に追われて買い物疲れしている方の参考になれば嬉しいです。
あわせて読みたい
過剰なまとめ買い以外の「やめてよかったこと」をご紹介しています。在庫管理以外にも暮らしを軽くする参考に読んでみてください。